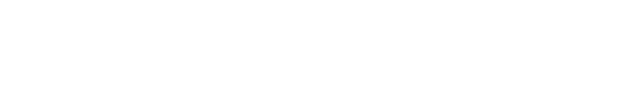月経時の痛み(月経困難症)
月経時の痛み、いわゆる生理痛は、多くの女性が経験する症状です。医学的には月経困難症と呼ばれ、日常生活に支障をきたすほどの強い痛みを伴うこともあります。ふじ産婦人科・内科では、患者さま一人ひとりの状態に合わせた丁寧な診察と、様々な治療法をご提案しています。月経痛でお悩みの方は、我慢せずに、お気軽にご相談ください。
月経困難症の症状について
月経困難症の主な症状は、月経時の下腹部痛です。痛みの程度は個人差が大きく、軽い鈍痛から、日常生活に支障をきたすほどの激痛まで様々です。痛み以外にも、以下のような症状が現れることがあります。
- 腰痛
- 頭痛
- 吐き気
- 下痢
- 疲労感
- 腹部膨満感
これらの症状は、月経に伴って現れ、2日程度で落ち着く方もいれば5~7日間症状が続く方もいます。症状が重い場合は、学校や仕事に集中できなくなるなど、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。
月経困難症の原因について
月経困難症の原因は、大きく分けて「機能性月経困難症」と「器質性月経困難症」の2種類があります。
機能性月経困難症
機能性月経困難症は、子宮や卵巣に明らかな異常がないにも関わらず、月経痛が起こるものです。主な原因は、月経時に子宮内膜で作られるプロスタグランジンという物質です。プロスタグランジンは、子宮を収縮させる作用があり、過剰に分泌されると、子宮の収縮が強くなり、痛みを引き起こします。また、プロスタグランジンは、血管を収縮させる作用もあるため、頭痛や吐き気などの症状を引き起こすこともあります。機能性月経困難症は、若い女性に多く見られます。
器質性月経困難症
器質性月経困難症は、子宮や卵巣の病気が原因で月経痛が起こるものです。代表的な病気としては、以下のものがあります。これらの病気は、子宮や卵巣の組織に炎症や腫瘍を引き起こし、月経痛を悪化させます。器質性月経困難症は、30代以降の女性に多く見られます。
■子宮内膜症
子宮内膜症は、子宮内膜に似た組織が、子宮以外の場所に発生する病気です。卵巣や腹膜、腸などに発生することが多く、月経時に出血や炎症を引き起こし、強い痛みを伴います。子宮内膜症は、不妊の原因となることもあります。
■子宮筋腫
子宮筋腫は、子宮の筋肉にできる良性の腫瘍です。筋腫の大きさや発生場所によって、月経痛や過多月経、頻尿などの症状が現れます。子宮筋腫は、不妊や流産の原因となることもあります。
■子宮腺筋症
子宮腺筋症は、子宮内膜の組織が子宮の筋肉の中に侵入する病気です。子宮が大きくなり、月経痛や過多月経、不妊などの症状が現れます。
■骨盤内炎症性疾患
骨盤内炎症性疾患は、子宮、卵管、卵巣などの骨盤内の臓器に細菌が感染して炎症を起こす病気です。下腹部痛や発熱、おりものの異常などの症状が現れます。骨盤内炎症性疾患は、不妊の原因となることもあります。
月経困難症の治療法について
月経困難症の治療法は、痛みの程度や原因、年齢、妊娠希望などによって異なります。主な治療法としては、以下のものがあります。
鎮痛剤
鎮痛剤は、痛みを和らげるための薬です。市販の鎮痛剤や、医療機関で処方される鎮痛剤があります。痛みが強い場合は、医療機関で処方される鎮痛剤の方が効果的な場合があります。
低用量ピル
低用量ピルは、女性ホルモンを補充する薬です。排卵を抑制し、子宮内膜の増殖を抑えることで、月経痛を軽減します。低用量ピルは、避妊効果もあります。
黄体ホルモン製剤
黄体ホルモン製剤は、黄体ホルモンを補充する薬です。子宮内膜の増殖を抑え、月経痛を軽減します。黄体ホルモン製剤には、内服薬、注射薬、子宮内留置システムなどがあります。
漢方薬
漢方薬は、体質や症状に合わせて処方される薬です。血行を促進したり、体を温めたりする効果があり、月経痛を軽減します。
手術
器質性月経困難症の場合、原因となっている病気の手術が必要になることがあります。子宮内膜症や子宮筋腫、子宮腺筋症などに対して、手術が行われることがあります。手術の方法は、病気の種類や進行度によって異なります。
生活習慣の改善
生活習慣の改善も、月経困難症の症状を和らげるために重要です。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけましょう。また、体を冷やさないように、温かい服装をしたり、入浴したりすることも大切です。ストレスを溜め込まないように、リラックスできる時間を持つことも重要です。
月経時の痛み(月経困難症)についてのよくある質問
Q1. 生理痛がひどくて、毎回鎮痛剤が手放せません。どうすれば良いでしょうか?
A1. 鎮痛剤を常用されている場合は、一度婦人科を受診されることをお勧めします。月経困難症の原因を特定し、適切な治療を受けることで、鎮痛剤の使用頻度を減らすことができる可能性があります。
Q2. 低用量ピルは、副作用が心配です。血栓症になりやすいというのは本当ですか?
A2. 低用量ピルには、吐き気や頭痛、むくみなどの副作用が現れることがありますが、多くの場合、服用を続けるうちに軽減します。ご不安な場合は、お気軽にご相談ください。低用量ピルの服用で、静脈血栓塞栓症の発症率が、わずかに増加することが知られています。もし、激しい頭痛や腹痛、胸痛、呼吸困難、視野の障害、言語障害、意識障害、ふくらはぎの痛み、などの症状が現れた場合は、すぐに服用をやめて受診をお願いいたします。静脈血栓塞栓症は、高血圧や片頭痛をお持ちの方、喫煙者では発症のリスクが高く、低用量ピルの使用開始後4カ月以内に起こることが多いので、注意が必要です。
Q3. 漢方薬は、効果が出るまでに時間がかかりますか?
A3. 漢方薬は、体質を改善することで、徐々に効果が現れることが多いです。即効性はありませんが、継続して服用することで、月経痛の根本的な改善が期待できます。