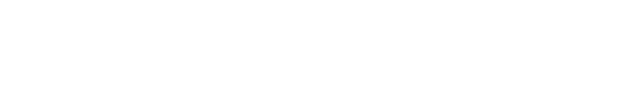内科(以下の疾患についてご相談ください)
内科専門医が対応します。
担当医:大友瞳
資格
・日本内科学会総合内科専門医
・日本糖尿病学会専門医・指導医
・日本甲状腺学会専門医
・日本内分泌学会内分泌代謝科専門医
・日本老年医学会老年科専門医・指導医
診療内容
糖尿病
「インスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とし、種々の特徴的な代謝異常を伴う症候群」と定義されます。つまり、インスリンの作用が十分でないためブドウ糖が有効に使われずに血糖値が普段より高くなっている状態のことです。初期には自覚症状が乏しく、長期間放置されることもありますが、血糖値が著しく高くなると、口渇、多飲、多尿、体重減少などがみられます。また、この高血糖が長く続くと、網膜症や腎症、神経障害などの合併症が出現し、さらに動脈硬化も進行します。もし治療しないで放置してしまうと、全身の血管や神経が障害を受け、様々な合併症が全身に起こる可能性がありますので、治療はできるだけ早期に開始する必要があります。治療は食事療法、運動療法、薬物療法を組み合わせて行いますが、まずは生活習慣の見直しが第一となります。治療目標は、良好な血糖管理を長期にわたって維持し、さらに体重や血圧、脂質も良好な状態を維持することにより、糖尿病を持たない人と同様の生活の質を保つことです。
妊娠と糖尿病
妊娠中に血糖値が高いと、母児に様々な合併症が起こりやすくなりますので、妊娠前からの血糖管理が大事になります。また、妊娠糖尿病という、妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病に至っていない糖代謝異常と診断されることもありますので、その場合はまずは適切な食事療法を行い、場合によっては薬物療法を行います。
高血圧症
収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧90mmHg以上を満たしたときに診断されます。自覚症状がない場合が多いですが、脳卒中や心疾患、慢性腎臓病などのリスクにつながります。生活習慣の見直しや降圧薬治療により、適切な血圧管理を長期間にわたって維持する治療を行います。
脂質異常症
動脈硬化の危険因子であり、脳卒中や心血管疾患を引き起こします。特に閉経後の女性は女性ホルモンの低下により、脂質異常症を発症しやすくなります。まずは生活習慣の改善を行い、必要に応じて薬物療法を行います。
甲状腺疾患:甲状腺中毒症(バセドウ病、甲状腺炎など)、甲状腺機能低下症(慢性甲状腺炎など)、甲状腺腫瘍、甲状腺腫など
甲状腺疾患は一般的に女性に多い疾患です。バセドウ病や慢性甲状腺炎のように典型的な自覚症状がある場合もありますが、甲状腺のはれやしこりのみが症状という場合もあります。バセドウ病などの甲状腺ホルモンが過剰に作られる病気では、動悸や多汗、手の震え、体重減少などの自覚症状が出現し、治療しないと心臓に負担がかかったり骨密度が減少したり、他にも全身に様々な症状が出てきます。一方、甲状腺機能低下症では無気力、易疲労感、寒がり、体重増加、便秘などの症状が出現しやすくなります。いずれも治療により甲状腺ホルモンが正常を維持できれば症状もよくなっていきます。また、妊娠においても甲状腺ホルモンの管理は重要になりますで、まだ妊娠を考えていない方でも、将来を見据えて早期の治療が大切と考えます。
当院では受診当日に甲状腺超音波検査を実施することができ、採血結果は翌日には出ますのでご相談ください。
妊娠糖尿病既往の方、